朝日記者の「書かずに死ねるか」
朝日新聞政治部記者野上祐氏の「書かずに死ねるか 難治がんの記者がそれでも伝えたいこと」(朝日新聞出版)にはうんざりするほど「記者」あるいは「政治記者」の表記が登場する。亡くなるまで「記者」であり続けようとする筆者の思いなのだろう。だからか、「記者」としての過去の業績も自慢げに語っている。
『世のありように「ひっかき傷」をつけることができたと今も誇りに思う「調査報道」が沼津時代に二つある』。野上氏は20年前の支局時代の”手柄”をそう書いた。
『一つは、ある市長選の取材を通じて、改正公職選挙法の「抜け穴」に迫ったものだ。候補者の中に、ほかの選挙で陣営から違反者を出した男性がいた。市長選への立候補は合法だが、グレーな印象はぬぐえない。なぜこうした立候補を許す抜け穴ができたのか。法改正に関わった総務省や当時の担当閣僚の証言を積み重ねると、こうした候補者が現れるのを誰も想定していなかった実態が明らかになった。
男性の当選を受け、自民党の森喜朗幹事長(当時、後に首相)、民主党の羽田孜幹事長(元首相)がともに「釈然としない」と述べた。抜け穴対策は一時、国政の課題と位置づけられた。
この件で恐ろしいのは、過去に同じような立候補例が1件あったことだ。だが、その地元の記者が反応せず、それきりに。すべては「おかしい」と素朴に感じる目玉の働きだ』
ずいぶんあいまいで具体性に欠ける説明である。これでは何のことか、読者には理解できないだろう。
1999年12月に行われた三島市長選挙の資料を引っ張りだしてきた。
20年前、三島市長選は全国ニュースに
野上氏が書く「抜け穴」とは、改正公職選挙法で拡大連座制(対象が秘書や運動員などに拡大)の適用を受けた候補の制裁が限定していることを指す。連座制の制裁範囲は「立候補禁止の期間は連座に関わった対象の選挙に限定している」
98年4月から三島市では特別養護老人ホーム開設にからむ汚職事件で逮捕者が続き、関与の疑いの濃かった市長が病気入院、辞職した。これに伴う市長選に、96年の衆院選に出馬、落選した寺院住職、小池正臣氏が立候補した。県議から国政選挙に打って出たが、伊豆半島の郡部での運動員が買収で逮捕、小池氏は拡大連座制適用となり、5年間衆院静岡7区への出馬を禁止された。
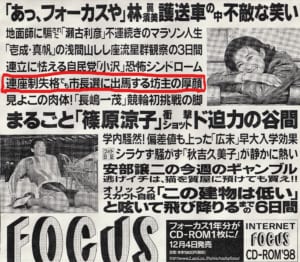
当時の「フォーカス」新聞広告。赤枠で囲んだのが、三島市長選の話題
小池氏の三島市長選へ立候補を「抜け穴」として、「法の精神に反する」と野上氏は厳しく批判した。地方版で何度も報道した記事を全国版にリライトして、夕刊1面トップ記事に仕立て上げたときにはびっくりした。この報道に対する反響は大きく、翌日には読売が追い掛け、朝日、毎日は社説でも「立法の精神に違反する」など批判、極めつけは写真週刊誌「フォーカス」が朝日の夕刊を持って取材に訪れ、「連座制失格でも市長選に出馬する坊主の厚顔」という記事を掲載、地方の市長選挙が一躍、全国レベルの話題になった。批判の渦の中で”連座制失格”候補は、大差で敗れるだろうとだれもが予測した。
反小池候補の最有力としてO県議が出馬すると、朝日は「連座制適用の小池氏を選ぶ良識を疑う」という記事を連日のように載せ、O氏支持を鮮明にした。前市長の後任と目された元市幹部、共産党女性候補による4人の激しい選挙戦が展開された。汚職の逮捕者が続いた街の再生ではなく、”連座制失格”候補への批判が選挙戦のテーマになった。
朝日の推すO氏優勢のまま終盤戦を迎えたが、候補者アンケートが地方紙に掲載されると形勢は一挙に逆転した。中心街のビル跡地活用について、O氏は「跡地活用は考えていない」と素っ気なく回答。圧倒的にO氏優勢が伝えられていたが、あまりの無責任さに市民の怒りを招いた。奇跡的な大逆転で、小池氏が3候補を大差で破り見事当選を果たした。
野上氏は翌日朝刊で『三島市長選「連座」元県議当選』(1面)、『連座再出馬 批判は埋没 制度の改善図る時期』(社会面)と全国版で報道、街の再生ではなく「連座制再出馬」批判をつらぬいた。
野上氏が著書に書いたように、総務省(当時は自治省)は本当に「このような候補を想定していなかった」のか?
朝日の「良識」と社会「常識」の違い
95年愛媛県議選で拡大連座制を適用され失職した元県議が98年4月に市議選に出馬して当選した。野上氏が「地元の記者は反応せず、それきりに。」と書いた過去の事例である。
当時の自治省選挙課を取材すると、「本人の罪と違い、拡大連座制による制裁を限定的にして、連座制を免れる方法を設けているのは憲法違反に問われないためにも必要」と説明した。最高裁の判断を含めて自治省の見解は合理的だったが、なぜか、朝日は「このような候補を想定していなかった」と書いた。
「抜け穴対策は国政の課題」(野上氏)だったはずだが、2003年民主党の都築譲代議士は連座制を適用され失職、その3年後、愛知県一色町長選に当選したのをはじめ、同じような立候補は数多く続いた。なぜか、朝日は2006年の都築氏出馬を含めて”抜け穴”立候補について、大々的な報道は行わなかった。
三島市長選での大騒ぎはマスコミによる地方選挙戦への介入に見えた。そんな逆風の中、なぜ、小池氏が当選したのか野上氏は取材しなかった。
「圧力感じたようだ」記事の裏側

当時の朝日新聞記事
「圧力を感じたようだ」。3段見出しの大きな記事が2000年3月3日朝日新聞地方版に掲載された。
三島市長選の翌年、1999年11月、場外舟券売り場建設計画にからみ伊豆長岡町長が百万円収賄の疑いで逮捕された。町長は一貫して否認、町には「町長を支援する会」が設立され、町民の7割を超える1万人以上の署名が集まり、議会の町長不信任案は大差で否決されるなど異常な事態が起きていた。
2月の初公判で町長は「全く身に覚えがない」と争う姿勢を見せ、拘留は3カ月に及んでいた。読売新聞によると、3月2日の第2回公判で贈賄側の会社役員の妻が出廷して、検察側の尋問で「(町長逮捕後に)『証言を変えろ。変えないと損害賠償請求する』というようなことを言われたことはないか」と質問。妻は「証言を変えろとまでは言われていないが」と否定した上で、✖✖(わたし)から「電話で『(町長の妻が経営する)旅館が暮れのかき入れ時なのに客が減り、損害が出ている。賠償請求すると言っている』と言われた」など証言した。
この公判後、野上氏は妻ではなく、代理人弁護士を取材、「証人威迫にあたるほどではないが、圧力は感じたようだ」と証言を得た。それで、最初に書いた「圧力感じたようだ」という大見出しが出来上がった。
当然、野上氏は知らなかっただろうが、贈賄側会社役員と逮捕の1年以上前から交流があり、わたしは何度も妻やその息子(町職員)とも会っていた。「お父ちゃんは町長に現金など渡していない」と最初に言ったのは、米屋を営む、その妻だった。伊豆長岡町の旅館が得意先であり、わたしよりも旅館の内情に通じていた。5月には町長夫妻が仲人で、息子の結婚式も予定されていた。
極めつけは、贈賄側が町長の旅館を訪れ、現金百万円を渡したという警察、検察の特定した日にちについて、数年前の手帳を探してきて、「お父ちゃんはその日は京都のお寺の会合に行っていた。寺の坊さんに確認してくれれば分かる」とその妻が教えてくれた。わたしは京都にあるその寺に出向き、同じ証言を得た。
「このまま、お父ちゃんが出てこないと、3千万円の仕事がダメになる。ごめんなさい」。それが妻からの最後の電話だった。否認すれば拘留が続くのは、カルロス・ゴーン氏の場合でおなじみだ。”自白”さえすれば、保釈され、なおかつ、贈賄事件の被告人は執行猶予付きの”微罪”判決を得る。第2回公判直前に会社役員は保釈された。
その後、現金授受の日に会社役員と一緒にいたと証言した京都の住職、同じ会合にいた他の僧侶らも証言を簡単に変えてしまった。会社役員の妻同様に彼らの都合で証言を変えたことをわたしが批判する術はない。
考えてもみてほしい。なぜ、検察側はその妻に「証言を変えろと言われたことはないか」などという不思議な質問をわざわざ法廷でしたのか?わたしが京都へ行ったことを検察官は妻から聞いていたはずだ。多くのことを知っているわたしを排除しなければあとあと面倒になると考えたのだろう。わたしは地方新聞社のサラリーマン記者であり、裁判に名前が出たことで汚職取材を一切禁じられ、直後の3月異動で本社内勤となった。その後町長は自ら辞職、町の支援ムードも一気に潮を引くように消えていった。
元町長は最高裁まで争ったが、贈賄側の証言を覆すことはできなかった。最高裁で有罪判決を受けたあと、元町長から送られてきた裁判の全記録に、唯一の頼みが、京都の寺院住職らの証言だったと書かれていた。野上氏の『すべては「おかしい」と素朴に感じる目玉の働き』では事実を見通せたはずもない。
「できる記者」とは?
「書かずに死ねるか」は、「できる記者っていうのはね」ということばから始まる。社内の交流人事で営業から記者になった入社4、5年目のことだという。「大事な話を聞いても、目が動かない」のが「できる記者」と書く。
今回、「書かずに死ねるか」を読んでいて、野上氏にとって「できる記者」であることが最優先だったことがわかる。もし、たった百万円の贈収賄事件の真実がどこにあるのか野上氏が突き止めたとき、「書かずに死ねるか」どうかは知らないし、書いたとしても元町長の有罪がひっくり返るどうかもわらかない。ただわかるのは、政治家を含めてすべての取材先が求めているのは、都合のよい「媒体(新聞紙面)」であり、「できる記者」かどうかは関係ない。贈賄側の会社役員、その妻、京都の僧侶たちなど個々の都合で「事実」は変わっていく。野上氏が属していた政治部記者の世界も都合によって「事実」そのものが変わるだろう。歴史にさまざまな見方があるように、「事実」はひとつではない。
「書かずに死ねるか」を読んで、新聞記者の「正義」とは何かをあらためて考えるきっかけになった。
野上氏は2016年1月ステージⅣのすい臓がんが見つかり、2018年12月28日に亡くなった。行年46歳だった。心からご冥福をお祈りする。

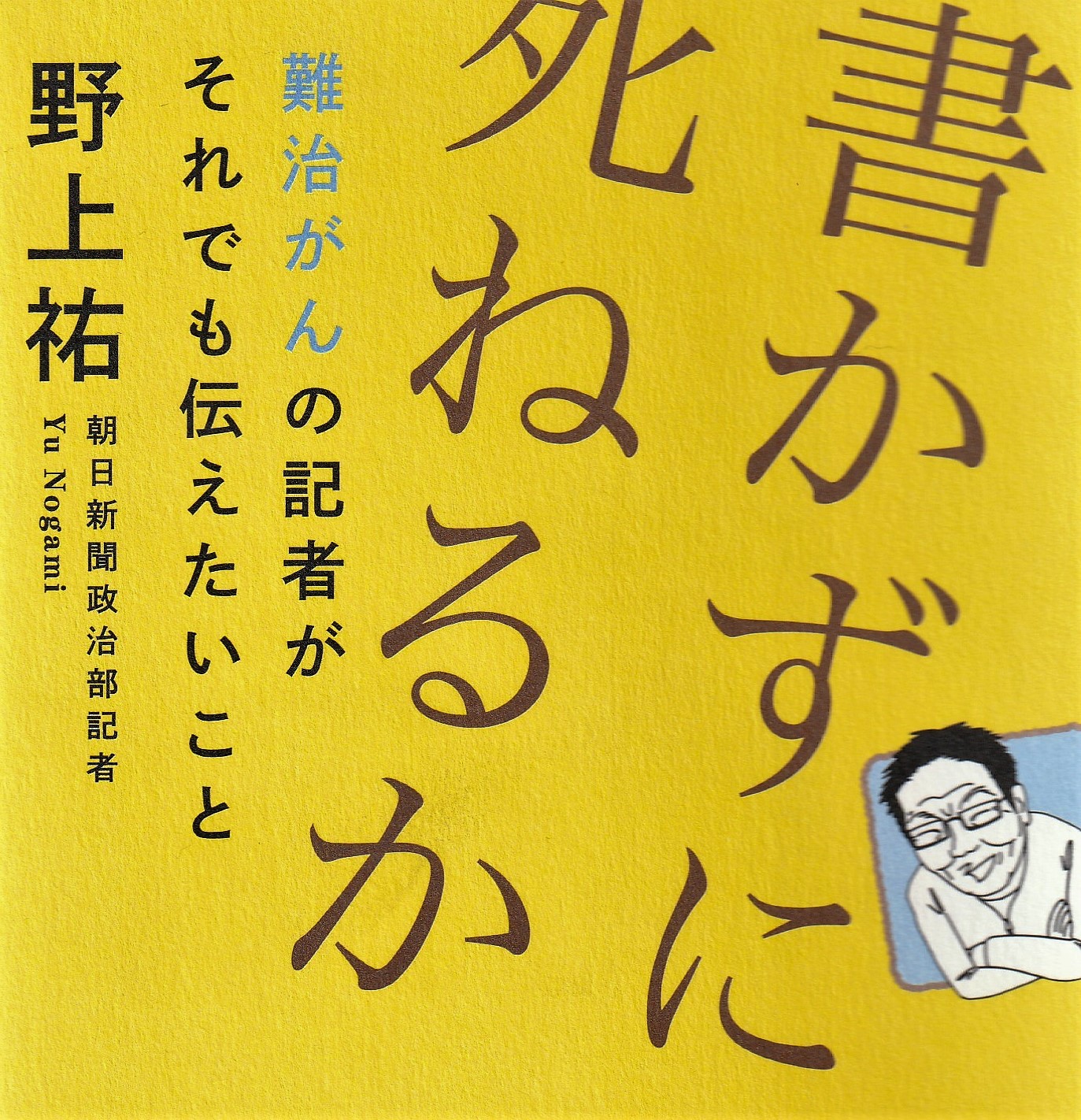










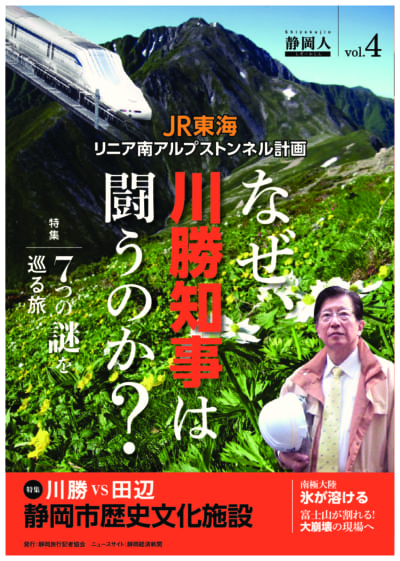


Leave a Reply