村上春樹訳「グレート・ギャツビーを追え」とは?
30年を区切りに新聞社を辞めてからは、環境と医療の2つのNPO法人、大学病院の広報担当理事、博物館副館長の傍ら、2つの雑誌を発行するなど自由な時間で仕事に向き合ってきた。コロナ禍の中、在宅勤務が推奨され、ようやくわたしのような仕事スタイルが認められるようになった。「コロナ後の世界」はどうなるのか?安定した生活もいいが、ワクワク、ドキドキしながら過ごすのも人生である。発見の始まりは、「旅行」だろう。第1回は、米国「プリンスントン大学」へ行ってみよう。

翻訳者村上春樹を強調した「グレート・ギャツビーを追え」表紙
ことし10月、ジョン・グリシャム著、村上春樹訳「グレート・ギャツビーを追え」(中央公論新社)が刊行された。プリンストン大学図書館地下に厳重に保管されている作家F・スコット・フィッツジェラルド(プリンストン大学中退)の長編小説の5つの生原稿が盗難に遭い、保険会社に雇われて、その行方を若い女性作家マーサー・マンが追うという物語である。アメリカでは有名作家の生原稿にべらぼうな値段がついている。5つの長編小説は2500万ドル(30億円くらいか)だから、文学芸術に対する価値観が日本と全く違う。小説追跡の舞台は、フロリダにあるカミノ島というリゾート地に移る。そこで独立系書店を営み、稀覯本を収集するブルース・ケーブルがもう一人の主人公として登場、カミノ島に住む個性的な作家たちと交流している。交流会にマーサーも招かれ、フィッツジェラルドの生原稿の行方を握るブルースの秘密を探りながら、次第にブルースの魅力にひかれていくという筋立てだ。有名作家の生原稿の価値とともに書店主の生活や地位もあまりに違うようだ。
あとがきで、村上春樹は2年ほど前、ポーランドを旅行している最中にクラクフの書店で、「Camino Island」というタイトルのペーパーバックを手に取り、裏表紙に書かれている筋書きに強くひかれて購入したという。それでようやく、わかった。何だ、「グレート・ギャツビーを追え」は「Camino Island」だったのか、と。
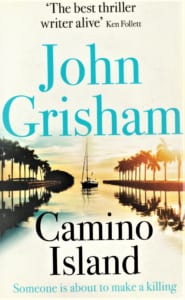
John Grishamが強調された
村上の2年ほど前と一致する。わたしは2018年1月頃、ペーパーバック版「Camino Island」をアマゾンで購入した。4月初旬から7月初旬までの3カ月間、アメリカ旅行へ行く前に、アメリカ小説1冊を原著で読んでみようと考えた。「法律事務所」「ペリカン文書」などグリシャムの小説を何冊も読んでいた。こちらは、すべて白石朗訳である。原書を読了するのも英語の勉強と覚悟を決めた。表紙に「針の眼」「大聖堂」などの作家ケン・フォレットが”The best thriller writer alive”(最高の推理小説作家、健在)の賛辞を寄せていた。「グレート・ギャツビーを追え」を購入後、「Camino Island」を引っ張り出してきて、もう一度、村上訳と比較しながら、読んだ。物語の中心が、本当はどこにあるのか表紙を比較するだけでもわかる。日本では、「村上春樹」と「グレート・ギャツビー」を強調しないと本の売れ行きに影響するのだろう。
わたしの場合、批評眼はあっても、肝心の英語力は非常に不足している。ただ、旅するだけならば、何とかなるだろう。そんな軽い気持ちで旅行に出たほうがいい。
「ディベート」を日本人の子供たちも学ぶべき!
「英語耳」ができていないのは、わたしたちの世代の問題か、それとももともとの能力不足なのか。大学卒業後もずっと英語とは全く無縁の世界で生活してきた。何度も英語圏へ旅行しているが、仕事のときは優秀な通訳がついた。自由になって時間が取れることもあり、アメリカ旅行を思い立って、英会話スクールと個人レッスンに参加、英語耳を何とかつくろうと努力した。「Camino Island」を読むのも、その一環だったが、英語耳づくりは全く無理で、グループレッスンでは隣の人が何を言っているのか、さっぱりわからなかった。
英会話の勉強をしながら、アメリカ旅行をすることができないか、いろいろ探して、3カ月の旅行プランを立てた。まずはニューヨークのお隣、ジャージーシティの大学が提供する、午前中は英会話レッスン、午後は、学生が公共交通を使ってニューヨークの名所を案内する2週間のプログラムに参加した。空港への送り迎え、宿泊付きでコロンビア人の60代男性の家にホームステイした。大学までバスで4、50分の隣町にある家主宅は、周辺道路にゴミが散乱する、治安も悪い地区だった。建築業を仕事とする主人は大のトランプ贔屓だった。「トランプ万歳」で友だちつきあいになれた。
わたしが入学する日に、若い日本男性、メキシコ、サウジアラビアからの4人とクラス分けの試験を受けた。英語耳はダメでも、筆記試験の点が良かったのだろう、上、中、下レベルのクラスで「中レベル」に入れられた。他の4人は「下レベル」だった。クラスの同級生はほぼ韓国人で、その他にタイ人などの10代の若者ばかり10人ほどだった。授業の中身はともかく、若い同級生らが話し掛けてこられても何を言っているのか、さっぱり分からなかった。ほぼ、単語で会話していた。
午後のニューヨーク名所見学は、地下鉄を使うのだが、案内の学生が複雑な地下鉄の路線に詳しくなく、スマホを見ながらでも国連本部へ行く道にも迷い、ずいぶん遠回りする始末だった。コロンビア大学のツアーでは、学生の説明はほとんど理解できなかった。まあ、自由の女神像、メトロポリタン美術館、ブルックリン美術館、エンパイアステートビルなどを見て、ああこんなものかと納得した。とにかく、毎日疲れて、危険な地区にあるコロンビア人の家に無事に戻って、ほっと安心、よく眠れた。アメリカの黒人たちが異様に太っていることだけはわかった。
次の目的地は、ニュージャージー州の田舎町。実際は、ニューヨークの近くでホームステイしながら、午前、英会話レッスン、午後は自由時間という3週間プログラムのはずだったが、ニューヨークから高速バスで約2時間は、「ニューヨーク近郊」ということらしい。
最初にスマホを購入して、ウーバーで車を呼ぶ方法を教えてもらった。タクシーなど走っていない地域だから、ウーバーがなければ、どこへも行けない。ウーバーを呼んだり、自分の位置がどこかなどアメリカはスマホがないと生活できない。日本では全く不要だから、戻ってからスマホは使っていない。
英会話とドイツ語教授で生計を立てるシングルマザーのミンディー家には、2人の小学生男児と女子高校生の3人の子供と猫がいた。

ナサニエルとミンディー母子
下の息子、10歳のナサニエルの小学校に行き、ナサニエルが参加する2対2の「ディベート(賛成と反対の側に立っての討論)」を傍聴した。前日、ナサニエルから、ディベートの概略を書いた資料をもらったから、目の前で何を討論しているのかは分かったが、当然、彼らの会話の詳しい内容までは聞き取ることはできなかった。
ディベートは「自由のための戦い」についてで、アメリカ独立戦争は、多くの犠牲者を出してまで自由のために戦う価値があったのか、どうかがテーマ。大した武器を持たずに戦い、死んでいったのは、無駄死にであり、無謀な戦いではなかったのか、「自由」と「人間の命」のどちらに価値があるのかがテーマである。愛国心を養う授業なのだから、多くの人の死に価値があったのだろうが、教師は口をはさまなかった。
クラスメートやPTAの前で、それぞれの主張をどのように展開するのか、これを10歳のときからやっていれば、日本の子供たちもずいぶん違っているだろう。リニア静岡問題の会議でも、一度、JR東海と静岡県専門部会委員が「ディベート」したほうがいい。将来の日本のためにリニアがいかに必要なのかJR東海が委員や流域住民たちを説得できるのか、どうかである。
先日の知事会見では、幹事社の記者がコロナ後の世界では、リニアは不要とまで言い出している。知事意見に引っ張られることなく、結論を導くには、ディベートが必要だろう。
プリンストン美術館は入場無料、写真撮影自由

インカの文化財(プリンストン大学美術館)
ミンディーの車で約30分ほどで、美しいプリンスントン市に到着する。3週間の滞在中に2度、プリンストンを訪れた。「Camino Island」を読んでいたが、まさか、舞台となったプリンストン大学に来るなど思ってもみなかった。ミンディーが毎週土曜日、プリンストンの教会で子供たちにドイツ語を教えていたから、それに便乗させてもらった。
大学が観光客に開放されているのは、プリンストンだけでなく、ニューヨークのコロンビア大学も同じだった。このあと、シアトルのワシントン大学、シリコンバレーのスタンフォード大学に行ったのだが、同じように観光客を迎え入れていた。特に、スタンフォードは中国人、韓国人らが大勢で訪れていた。静岡県立大学は、お隣の県立美術館とともに開放して、学生たちがツアーガイドをやれば、それなりの見どころはありそうだ。
タイトル写真は、プリンストン大学のガイドツアーの光景。2頭のトラはシンボルであり、大学構内でいくつも見られる。

セザンヌの「セント・ビクトワール山」
プリンストン大学美術館は入場無料で、そのコレクションは日本の美術館に比較できないほどにすばらしい。「セント・ビクトワール山」などのセザンヌコレクションは特に有名。ボッシュ、ゴッホ、ルオーなどの傑作がさりげなく並んでいた。写真撮影も自由だから、うっとうしい監視員の注意もなく、パンフレットをもらい、十分に理解できた。そして、何よりも日本コーナーがあり、聖徳太子立像だけでなく、白隠禅師の大胆な掛け軸五振りの展示には驚いた。
2度目の訪問時にも美術館を訪れたが、あまりにも見る作品が多く、それにメトロポリタン美術館のように観光客で混雑しているわけでもないから、本当に美術鑑賞をするならば、ぜひ、プリンスントンまで足を延ばすのがお薦めだ。
池田真紀子訳「パチンコ」もことしのお薦め!
「Camino Island」を読んでいて、アメリカでの文学作品の生原稿や有名作家の初版本の価値の違い、作家の書店回りなどに驚いたが、プンリンストン市の図書館に行ってみて、図書館の機能が日本と違うのにもびっくりした。当時の企画テーマ「移民」の文学作品の紹介や講演会、本のレクチャーなど多彩に行われ、独自に制作した「図書館だより」も立派で読ませるところが多かった。
大きな注目を集めていたのは、韓国系米国人の女性作家ミン・ジン・リーの「Pachinko」。韓国から日本への移民がテーマである。この本の紹介やレクチャー講座が3月に開かれ、4月には作者のリーを招請して、講演会が行われた。日本の講演会と違うのは、作者の話は最初の20分弱だけで、あとの1時間以上は参加者とのディスカッションになることだ。日本の場合、参加者の質疑等はほんの5~10分程度と違い、会場の疑問や本の感想等に答えるのが講演会のようだ。
ことし7月、「Pachinko」は、池田真紀子訳「パチンコ上、下」(文藝春秋)で出版された。四世代にわたる在日コリアンの苦闘を描いたとあらすじが紹介されている。まあ、日本人に抵抗感のある難しい話ではなく、肩の凝らない大河小説として読める。
わたしが読んでいたタイミングで、山口県の80代保険外交員が19億円を顧客から不正取得したニュースが流れていた。小説「パチンコ」では、「家計にゆとりのない孤独な主婦に高額な生命保険を販売していた」と「生命保険」と「パチンコ」を比較して、ギャンブル性は全く同じだと指摘している。生命保険販売はパチンコ業と違い、非常に社会的な地位が高いと勘違いしている身内に腹を立てている主人公の思いが吐露される。
「どちらも確率と孤独を利用してお金を儲ける仕事だ。従業員は毎朝、パチンコ台に微妙な調整を加え、それが結果を左右するーゲームに勝つのはほんのひと握りで、ほかの全員が負ける。それでも人はやはりゲームを続ける。自分こそ幸運なひと握りかもしれないと期待する」(小説「パチンコ」から)
生命保険金も同じことで、旦那が亡くなって多額の保険金をもらえるのはほんのひと握りなのに、毎月高い保険料を支払っている。パチンコと同じく、保険もギャンブル性が高いと言いたいのだ。アメリカには「パチンコ」は存在しないが、小説「パチンコ」は百万部以上を売った。
今週はリニア問題の動きはなく、ことし読んだ2冊の本にまつわる旅の話を書いた。ジョン・グリシャムの新作「Camino Winds」はアメリカではベストセラー入りしているようだ。村上春樹はあとがきで中央公論新社から翻訳本が発売されると書いているから、ぜひ、ペーパーバックを読んでから、アメリカ旅行をお薦めする。その2年後くらいに、日本で翻訳本が出るはずだ。「Camino Island」を読み、プリンストンへ。そして、「Camino Winds」を読んで、フロリダへも足を延ばせば、きっと、ワクワク、ドキドキに出会えるだろう。









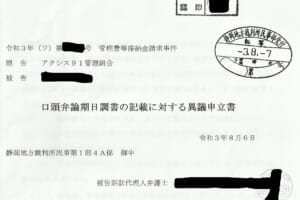


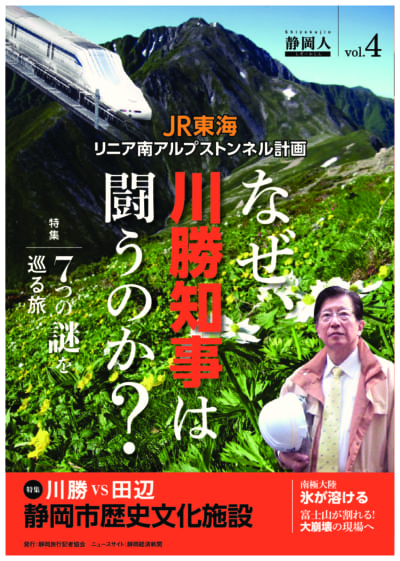


Leave a Reply